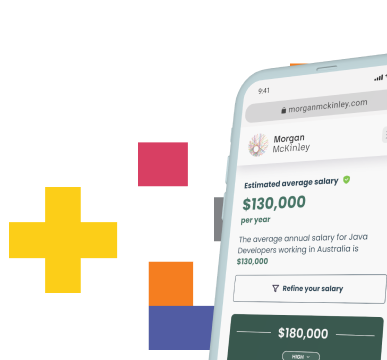データが示す実態:ハイブリッドワークは従業員満足の鍵か?

ハイブリッドワークは働き方改革の最適解か、それとも生産性を低下させる落とし穴か?
在宅勤務と出社を組み合わせた「ハイブリッドワーク」モデル。賛否は分かれるものの、転職希望者の間ではすでに“要検討事項”として定着しつつあり、今や無視できない働き方となっています。
企業が優秀な人材を惹きつけ、持続可能な勤務制度を設計していくためには、従業員と企業、それぞれのニーズや期待のバランスをいかに取るかが鍵となりそうです。
データで見る現状:ハイブリッドワークの人気度
以下は、Morgan McKinley が世界の働き手2,751名と採用担当者530名を対象に実施した調査結果から明らかになった傾向です。
まず、理想とする出社頻度について尋ねたところ、次のような結果となりました:
- 週1〜2回の出社が理想:45%
- 週3〜4回がベスト:30%
- 毎日出社したい:わずか9%
また、現在ハイブリッド勤務中の人のうち、88%が「この働き方を続けたい」と回答。満足度の高さがうかがえます。
一方、フルタイム出社の人は満足度が低く、約68%がハイブリッド勤務への移行を希望しています。「この働き方を続けたい」という人は30%にとどまりました。

働き手と企業の間に広がる温度差
ハイブリッド勤務を希望する働き手が多い一方で、企業側の温度感はやや異なります。Morgan McKinleyの調査によると、
- 回答企業の24%が昨年よりもオフィス出社日数を増やす方針を示しています。
こうした働き方に対する認識のズレにより、ハイブリッドワークを認めない企業は次のようなリスクを負うことになります。
- 職場としての魅力が薄れ、優秀な人材の確保・定着が難しくなる
- ハイブリッドワークが可能な企業への転職を検討する社員が出るなど、人材流出リスクが高まる
- 社員の不満から会社や仕事に対するエンゲージメントが下がる

ハイブリッドワークをしている働き手(46%)に比べ、完全出社組だけでなく、完全在宅組も転職に積極的(58%)という結果も興味深いところです。完全在宅では職場やチームとのつながりが薄れやすく、「誰のために、何のために働いているのか」といった目的意識の希薄化が影響しているのかもしれません。
勤務制度の設計においては、ハイブリッドワークを希望する働き手が多いことにも配慮し、従業員満足度を高めるための工夫が欠かせません。
若手だけ出社?ハイブリッドワークの公平性の問題
Morgan McKinleyの調査では、職位によって働き方に差があることも明らかになりました:
- ジュニアや担当者レベルでは49%がフルタイム出社
- ベテランや管理職ではフルタイム出社をしている人はそれぞれ23%、28%
ベテランは仕事の要領がわかっていて、自律的に業務を進められるという事情はあるでしょう。ですが、「若手は現場で学ぶべき、上位職はリモートでよい」という構図は人材の育成やナレッジ共有の観点からベストとは言えません。
特にジュニア層には上司や同僚との接点を意識的に設けることが重要です。
ハイブリッドワークの「正解」は存在しない
ハイブリッドワークの普及状況にはばらつきがあります。
当社の調査では次のような結果が得られました:
- 週5日出社するという回答者は営業・マーケティングでは24%
- IT/テクノロジーでは19%
- プロジェクトマネジメント&コンサルではわずか11%
このことからもわかるようにどの会社・部署にも一様に適用できる唯一無二の「正解」は存在しません。リモートワークやハイブリッドワークが適している業界や部門もあれば、社員がオフィスや現場に常駐しなければ立ちいかない業務もあるからです。
ハイブリッドワークに適している業界・職種としてはIT/テクノロジー、プロジェクトマネジメントやコンサルティング、営業・マーケティングなどがあります。

一方製薬・自動車業界の専門職や物流など領域では、週5で出社している人が比較的多いことがわかります。
大多数の働き手がハイブリッドワークを希望している事実を踏まえつつ、業界や部署固有のニーズに丁寧に寄り添う必要がありそうです。
従業員満足度に直結する「柔軟な働き方」
ハイブリッドワークやフレックスタイム制度などの柔軟な勤務制度は従業員のエンゲージメントや満足度、定着率に直結しています。
- 42%の採用担当者が「柔軟な制度が人材の惹きつけ・定着に効果的」と回答
- 直近半年で人材流出を経験した採用担当者の74%が 「給与・待遇への不満」と「柔軟性の欠如」に原因があったと分析
また、在宅勤務制度やハイブリッドワークといった勤務環境や現職の福利厚生について、従業員の満足度を調べたところ、週5日出社している社員の満足度が最も低い結果となりました。週5出社している働き手のうち、26%が「不満」または「非常に不満」と回答しています。同様の回答はハイブリッドワーカーでは18%、完全在宅の人では19%でした。
また、「今のポジションは安定していると感じますか?」という質問に対しては、ハイブリッド勤務をしている働き手は51%が「安定している」と回答し、「不安定である」(29%)を大きく上回りました。
興味深いことに、「不安定である」という回答が最も多かったのは完全在宅勤務の働き手(38%)でした。会社や上司の様子がわかりづらいことが不安感につながっている可能性があります。

このような不安を解消するには、企業はリモートワークをしている従業員とのコミュニケーションに細心の注意を払う必要があるでしょう。
この結果から、出社と在宅を組み合わせたハイブリッドワークは従業員満足度や安心感の点からも最良のアプローチであるといえそうです。
中小企業こそハイブリッドワークを武器に
ハイブリッドワークは、中小企業にとっては優秀な人材を獲得するための大きなチャンスです。
大企業に比べて融通が利きやすく、求職者が求める勤務制度の「自由度」や「柔軟性」を提供しやすいことが人材獲得競争において強みになります。
転職希望者の間では、このような「働きやすさ」を重視する人が増えています。
給与面では大手に勝てなくても、柔軟な勤務時間やスピーディな意思決定ができる環境が、人材を引き寄せる大きな魅力になるでしょう。

ハイブリッドワーク導入で企業が直面している課題とは
多くの企業が在宅勤務を取りやめ、再び社員の出社を求めるようになっている背景には、さまざまな理由があります。
【社員に再び出社を求めている理由】
- 最も多かったのは「社員同士のコラボレーションを促進するため」
- 次いで「企業文化を強化するため」「パフォーマンスを向上させるため」が続きました。
ハイブリッドワークには多くの利点がある一方で、課題も存在することを示す結果といえます。
在宅で勤務をする人と出社している人が混在するハイブリッド環境では社員間のコミュニケーションが不足しがちです。ですがコミュニケーション不足によって生産性が下がってしまったのではハイブリッドワークを導入した意味がありません。
もう一つの課題が社員のウェルビーイングです。ハイブリッドワークはワークライフバランスの向上に寄与する反面、孤立感や燃え尽きといった問題を引き起こすこともあります。
社員が分散していると、企業文化やチームの一体感が希薄になりがちです。リモート・チームビルディングの取り組みや定期的なフォローアップなど、クリエイティブな発想や丁寧なサポートが大切です。
この他にも様々な課題があります。
- 法務・コンプライアンスの問題:社員が様々な場所・国で働く場合、労働法、税制、個人情報保護の対応がより複雑になります。
- 新入社員オンボーディング:新卒やエントリーレベルのポジションでは対面での学びが重要ですが、リモートではその自然な知識共有が難しくなります。
- IT環境のばらつき:すべての社員が在宅勤務に必要な技術や設備を持っているとは限らず、作業環境や通信品質の差が生産性に影響します。
- セキュリティリスク:リモートワークはサイバーセキュリティの脅威を増大させるため、堅牢なセキュリティ対策と社員教育が不可欠です。
- インクルージョンと公平性の確保:ハイブリッド勤務が特定の社員層に不利益をもたらさないよう、制度設計にも配慮が必要です。
- ハイブリッドモデルへの移行の難しさ:従来の出社型モデルからハイブリッドへの移行には、方針やプロセス、文化の見直しが求められます。
ハイブリッドワークの新入社員には、定期的なオンライン面談、オンライン研修やメンタリング、コミュニケーション手段の充実など、体系的なサポート体制を築くべきでしょう。
ハイブリッドワーク成功の鍵を握るのは「マネージャー」?
新しい働き方には、新しいマネジメントが求められます。
バーチャルチームのマネジメントにあたっては、企業は新たな生産性管理ツールを取り入れたり、コミュニケーションツールの活用方法を見直したりして、信頼関係の構築を目指しています。

在宅勤務ではマネージャーと部下が離れて働くからこそ、データが両者をつなぐ重要な手段になります。
仕事の進み具合や成果を「見える化」することで、お互いの信頼関係が深まり、チーム全体の成功にもつながるのです。
「ただ監視するのではなく、業務を正しい方向に導き、目標を達成することが目的です。」

ハイブリッドワークやリモートワークでは、「勤務時間」ではなく「成果」に焦点を当ててチームを導かなければいけません。
こうした中でマネージャーはチームのエンゲージメントを維持し、つながりを促し、企業文化を意識的に育み、メンタルヘルスの問題にも対応するなど、重要な役割を担うことになります。
納得感のあるハイブリッドワーク・モデルを
ハイブリッドワークを成功させるためには、
「ハイブリッドワークがうまく機能するためには、自分に何が求められているのか?」
「自分の役割を果たせなかったら全体にどのような影響があるのか?」
を会社側・従業員側、管理職・部下それぞれがきちんと理解し、果たすことが要となります。
企業と従業員が同じ方向を向いて制度を作り上げれば、柔軟かつ安定した生産性の高い組織が実現できるでしょう。